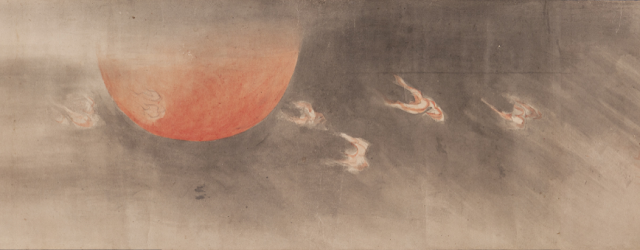「鬼胡桃」、「鬼教官」。大きいものや怖いもの表すときに言葉の頭に「鬼」をつけることがあります。一方で「鬼〇〇」という用法はそれだけでなく、若者言葉としてもつかわれ続けているようです。
言葉の年鑑『現代用語の基礎知識2020』の若者用語の解説をのぞいてみると、「意味、使用法の進化系」のカテゴリに「鬼」が「とても。やばいくらい。」という強調表現として採集されています。過去の『現代用語の基礎知識』をめくってみると、2006年くらいからこのような説明で「鬼」が記載されています。
もう少しさかのぼってみると、1989年には「鬼ざん」という言葉が載っていました。解説には「鬼のような残業。デートなどの約束がある時にいや応なしに押しつけられる残業。」とあります。鬼のような……拘束時間や内容が長い・重いというところでしょうか。ここでは「残業」自体がネガティブワード、というのもありますが、「鬼」自体もどちらかというとネガティブなイメージをもってつかわれていそうですね。
翌年の90年には、「鬼」単独で採録されています。解説には、「ものすごく、鬼ごみ、鬼ぶす」とあり、こちらの用例もマイナスイメージの単語の強調になっています。
用例に変化が出てくるのは94年からです。「鬼うま、鬼かわ、鬼ごみ、鬼こわ、鬼すご、鬼だる、鬼へん(へんてこ)」と用例のバリエーションが一気に増え、ポジティブな単語にもつかわれています。
ちょっとくすっとしてしまったのが98年。「鬼」が採録されているカテゴリは「超強調」。「いくら強調してもし足りないほど言葉が不足している」とことばが添えられていました。
さて、『現代用語の基礎知識』2010年~2020年には「鬼○○は最上級を意味する。」と書かれていますが、ここまで『現代用語の基礎知識』に頼りすぎてしまったので、ここで少し視点をひろげて「鬼」用例を拾ってみたいと思います。若者言葉としての「鬼○○」は2010年代に入ってさらに広がりを見せているようです。
「鬼コ」
これは2015年「ギャル流行語大賞」(GRP by TWIN PLANET)で6位にランクインした言葉です。聞きなれない方は「コ」が何を意味するのか考える楽しさがありますね。どんな意味でしょう。
正解は、鬼コール。ひたすら電話をかけ続けること、でした。
(隣の先輩いわく「鬼電」ならわかるけど!「鬼電」なら!!!)
続きましてギャル雑誌eggの「egg流行語大賞2018」(株式会社MRA)にはこんな「鬼」用語がふたつランクインしています。
6位「鬼盛れ」
2位「鬼パリピ」
「鬼盛れ」は「すごく盛れる事」とあります。ちなみに「盛る」は物理的に高さ、大きさを出していく・(話を)おおげさにいうという意味もありますが、最近はSNSにあげる写真映えなども関係してきらびやかする・見栄えをよくするという意味でも使われているように思います。「鬼盛れ」したらテンション爆アゲよいちょまるですね。
さて、学芸課鬼殺係のメンバーでふと、「鬼」って言葉としても滅びずに現役だよね、なんて話から意識し始めた「鬼」若者言葉ですが、今回初耳で悔しかったのが最後にご紹介の「鬼パリピ」です。
こちらは「鬼」よりもさらに上級表現。「鬼パリピかわいい!」(とんでもなくはちゃめちゃにかわいい!)などという使い方をします。ここでの「パリピ」、パーティーピーポーの略語も強調表現の一種なのだそうで、「鬼」+「パリピ」ということで、それは大変な強意を感じます。うーん、若者言葉の勢いの凄まじさには、もはやぴえんこえてぱおん。
ということで、「鬼」は若者言葉の強調表現として、少しずつ用法を変えながら少なくともここ30年ほどつかわれ続けてきたようです。その用例を見ているとポジティブな意味にも多くつかわれています。
まさに、「いくら強調してもし足りないほど言葉が不足している」若者にとって「鬼」とは、良いも悪いもなく、ただただ物足りなさを補うときの心強いアイテムなのかもしれません。
「鬼」しか勝たん!
企画展「鬼は滅びない」連載ブログ担当ひとこと裏話、これにて閉幕……!
(学芸課鬼殺係・さとう)
■企画展「鬼は滅びない」は2021年6月13日(日)まで開催中。
※緊急事態宣言の発出を受け、5月31日(月)まで閉室中です。