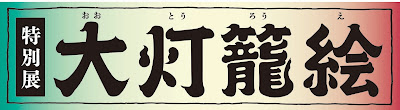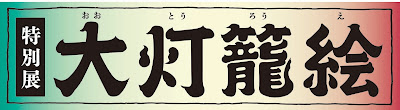|
| ただいま開催中 いよいよ11月4日(月・振休)まで 会場:福岡市博物館 特別展示室 |
特別展「大灯籠絵」、いよいよ最終日が近づいてきました。
早いものです。
このブログも25回目。長かったような、瞬く間だったような……
さて、ブログその23では、成長する展示についてお伝えしました。
実は、その後も「成長」がとまらないのです。
先日は、福岡市東区の方から、
「むかしお地蔵様のお祭りで飾っていたかもしれない大灯籠絵みたいなのがでてきました」
とご連絡をいただき、担当学芸員Kが小躍りしながら調査に出かけました。
拝見したところ、まさに「大灯籠絵」だと判明し、
あらためて詳しく調査するお約束もでき、
担当学芸員Kはよく分からない歌をくちずさみながら、大興奮で帰ってきました。
また、三大「大灯籠絵」絵師(一得斎高清、海老﨑雪渓、白水耕雲。筆者が勝手に選定。)の一人、海老﨑雪渓の子孫の方からもご連絡をいただきました。
なんと「雪渓の遺品の羽織がある」とのこと。
みせていただくと、羽織の裏には、龍が描かれています。
雪渓のサインはないものの、
ブログ23で紹介した子ども用の山笠法被の龍とも雰囲気が似ていて、
「雪渓が自分で描いた絵かも?!」と、期待が膨らんでいます。
このように、この特別展「大灯籠絵」、まれにみる成長を続けています。
成長は展覧会閉幕後も続いていきそうです。
成長の成果は、また改めて、何らかの形でご報告ができるのではないかと思います。
どうぞ、お楽しみに!!
その前に、「大灯籠絵」が一堂に集まる希少な機会ですので、
ぜひぜひ、特別展「大灯籠絵」の会場へもお越しください。
11月4日(月・振休)まで開催中です。
(by おーた)